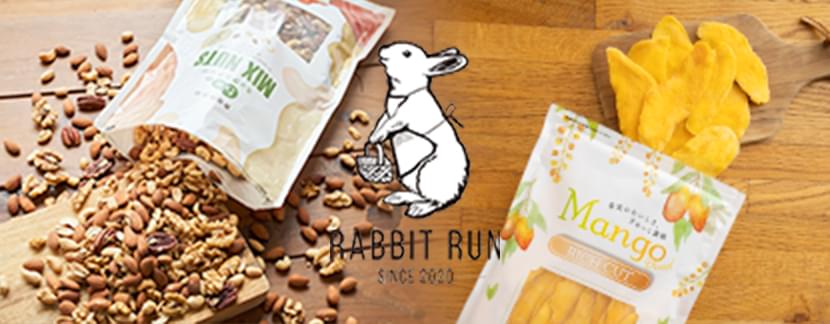SF小説家・野尻抱介氏が、原始的な遊びを通して人類のテクノロジー史を辿り直す本連載。
人工知能や仮想現実などなど、先進技術を怖がらず、翻弄されず、つかず離れず「ぱられる=横並び」に生きていく。プレ・シンギュラリティ時代の人類のたしなみを実践します。
1章 幻の鉱物
論文は韓国で20年あまり非公開で研究していたものを、メンバーの一人が独断でプレプリントサーバーに流したもので、その出自をみても、ちょっと怪しかった。
プレプリントというのは査読を経ていない論文のことで、信頼性が低い。しかしプレプリントは新鮮な情報なので、これをもとに議論されることは普通にある。AI関連など、進捗が著しい分野で話題になるのはもっぱらプレプリント論文だ。
誤ってはいたが、LK-99は常温核融合やSTAP細胞事件のような研究不正ではないようだ。研究不正はその界隈をスポイルするが、今回のケースは、むしろ界隈を活性化したように見えなくもない。
クラークの『楽園の泉』というSF小説は「もし軌道エレベーターができたら」というビジョンを世界中に広め、現実の研究開発を喚起した。同様にLK-99は「もし常温常圧超伝導物質ができたら」というビジョンを広め、SF小説としての役割を果たしたのではないだろうか。もちろんこれは結果論であって、学術論文がSFじゃ困るのだが。
「日本で鉛が出るところといえば……神岡鉱山の清五郎谷に方鉛鉱が掃いて捨てるほど積んであったなあ」
と、思い出した。
四半世紀ほど前、私は鉱物採集に熱中していた。方鉛鉱は私の好きな鉱物で、メタリックな輝きと明瞭な劈開を持っており、手に持つとずしりと重い。
 LK-99の材料であるラナルカイトは方鉛鉱の酸化生成物だから、私は材料の半分をすでに手中にしていた――と言えなくもない。これとリン酸銅を乳鉢でごりごりやって粉末にして1:1でまぜて電気炉に入れたらLK-99ができるはずだ。電気炉の入手も考えたが、もたもたしているうちにLK-99はハズレという結論が出てしまった。
LK-99の材料であるラナルカイトは方鉛鉱の酸化生成物だから、私は材料の半分をすでに手中にしていた――と言えなくもない。これとリン酸銅を乳鉢でごりごりやって粉末にして1:1でまぜて電気炉に入れたらLK-99ができるはずだ。電気炉の入手も考えたが、もたもたしているうちにLK-99はハズレという結論が出てしまった。鉱物学は役に立つ知識だ。どれくらい役に立つかといえば、NHKの人気番組『ブラタモリ』に出てくる科学は地学(地球科学)で、そのサブジャンルである鉱物学も頻繁に参照される。大衆向けTV番組が成立する程度には、人類の生活・社会・文明に結びついた、浸透力の強い学問だとわかる。
鉱物を知ることは、この物質世界を理解する手がかりになる。鉱物採集をしていたおかげで、私は固体天体に関する研究者の話にもそこそこついていけた。これは私の本業を大いに助けてくれた。

 方鉛鉱を固定し、細いニクロム線を触れるか触れないかぎりぎりぐらいの軽さで接触させると、点接触ダイオードのように機能する。これを通すと、放送電波に重なっていた音声信号が取り出せて、電波が持っているエネルギーだけでクリスタルイヤホンを鳴らせる。ニクロム線を調整するうち急にラジオの音が大きくなるのは感動的だ。
方鉛鉱を固定し、細いニクロム線を触れるか触れないかぎりぎりぐらいの軽さで接触させると、点接触ダイオードのように機能する。これを通すと、放送電波に重なっていた音声信号が取り出せて、電波が持っているエネルギーだけでクリスタルイヤホンを鳴らせる。ニクロム線を調整するうち急にラジオの音が大きくなるのは感動的だ。2章 採集旅行
神岡鉱山の亜鉛・鉛・銀の採掘は2001年で終了した。現在はその地下空間を利用したニュートリノ観測施設カミオカンデや、重力波望遠鏡KAGRAで知られる。
私が清五郎谷に行ったのは1995年で、まだ稼鉱中だった。知人と数人で訪ねたのだが、山の中の未舗装の悪路を15kmも走ることになって大変だった。途中の急坂では私の軽バンが登れず、同行者に後ろから押してもらってなんとか乗り越えた。


ハンマーはミネラルハンターのシンボルだ。使い方は『天空の城ラピュタ』のポムじいさんがお手本になる。片手で石を持ち、ハンマーの平たいほうで素早く叩く。鉱物用のハンマーは一方がピッケルのように尖っているが、そちらで叩いてはいけない。
 私は代々木の岩本鉱産物商会で買った500gと1kgのハンマーを愛用している。この店は数年前に廃業して、商品はニチカが引き継いでいる。
私は代々木の岩本鉱産物商会で買った500gと1kgのハンマーを愛用している。この店は数年前に廃業して、商品はニチカが引き継いでいる。 写真のルーペは最近のもので、アニメ『恋する小惑星』のプレゼント企画でもらったビクセンのMT19だ。声優の指出毬亜さん、東山奈央さんのサイン入り。しかし飾り物にするのは惜しいので、サインをクリアラッカーでコーティングして使っている。
写真のルーペは最近のもので、アニメ『恋する小惑星』のプレゼント企画でもらったビクセンのMT19だ。声優の指出毬亜さん、東山奈央さんのサイン入り。しかし飾り物にするのは惜しいので、サインをクリアラッカーでコーティングして使っている。ルーペの使い方は同アニメの桜井先輩が模範を示している。このような高倍率のルーペは虫眼鏡のように構えてはだめで、眼にできるだけ近づけて使う。ルーペは常に持ち歩いていて、すぐに取り出せる。岩石鉱物の研究経験はこの所作でわかる。



神岡町の市街を流れる高原川の河原でも、閃亜鉛鉱などが拾えたから、訪ねてみるといいだろう。閃亜鉛鉱はずっしり重いので、持っただけでも只者ではないとわかる。
鉱山や鉱物産地の近くに行くと、道端の石が怪しい気配を放つように感じるものだ。ポムじいさんが「石たちが騒ぐのでな…」と語る場面は、鉱物採集をする人なら共感を覚えるだろう。
3章 鉱物の見分け方
鉱物鑑定は、一筋縄ではいかない。これは入門者必携の書『楽しい鉱物学 基礎知識から鑑定まで』(堀 秀道、草思社)の受け売りになるが、つまりこういうことだ。
鳥や昆虫なら図鑑を調べて、外見を見比べればわかる。鉱物も美麗な結晶になっていれば見分けやすいのだが、実際には地味な石ころであることが多く、図鑑の写真と見比べても判然としない。岩石と鉱物は、図鑑が役に立ちにくい分野なのだ。堀氏は実物の標本を集めてそれを図鑑にすることを提唱している。
 外見でわからなければどうするかというと、いろんな方法を組み合わせる。硬度、比重、条痕、炎色反応、蛍光、劈開、屈折率、塩酸による発泡、磁性などなど。外見についても、透明度や光沢の質、結晶面のなす角度などの着眼点に留意して調べる。
外見でわからなければどうするかというと、いろんな方法を組み合わせる。硬度、比重、条痕、炎色反応、蛍光、劈開、屈折率、塩酸による発泡、磁性などなど。外見についても、透明度や光沢の質、結晶面のなす角度などの着眼点に留意して調べる。文明の利器、X線回折装置なら絵合わせで組成が推定できて強力だが、個人ではおいそれと扱えない。そこで伝統的な方法を使うのだが、どれかひとつの方法で同定できることはまずない。比重がこれだけで、硬度がいくつで、炎色反応で緑だから銅を含むらしい――と組み合わせて絞り込んでゆく。器具もいろいろ使うので、いつの間にか上の写真のようになった。器具を収納する箱も自作して、採集のときは車に積んでゆく。
手元にある分析方法と器具を以下に挙げよう。
 この箱は「モース硬度計」と言うが、硬度比較用のサンプルを収めた標本箱だ。調べる鉱物をこのサンプルで引っ掻いて傷がつけば、硬度はサンプル以下、とわかる。サンプルをより硬度の低いものに換えて引っ掻くテストを繰り返す。
この箱は「モース硬度計」と言うが、硬度比較用のサンプルを収めた標本箱だ。調べる鉱物をこのサンプルで引っ掻いて傷がつけば、硬度はサンプル以下、とわかる。サンプルをより硬度の低いものに換えて引っ掻くテストを繰り返す。 鉱物の表面は風化などで色がわかりにくい。条痕板という白い陶器の板に鉱物をこすりつけると、本来の色が現れる。岩絵の具の色と考えてもいいだろう。写真は神岡で拾った閃亜鉛鉱の条痕で、赤褐色になっている。
鉱物の表面は風化などで色がわかりにくい。条痕板という白い陶器の板に鉱物をこすりつけると、本来の色が現れる。岩絵の具の色と考えてもいいだろう。写真は神岡で拾った閃亜鉛鉱の条痕で、赤褐色になっている。「これは未来を占う試金石となるだろう」という言い回しがあるが、実物を知る人は少ないだろう。試金石(touchstone)は金の純度を調べるための黒い条痕板だ。Amazon等で買えるので、お手持ちの指輪などをこすりつけてみてはいかがだろうか。
 石灰岩など炭酸カルシウムを含む鉱物に希塩酸を垂らすと、ビールのように音を立てて泡立つ。写真は方解石だ。石灰岩は広く分布しているので、それとわかれば有力な判断材料になる。採集時も希塩酸を目薬容器に入れて持参する。
石灰岩など炭酸カルシウムを含む鉱物に希塩酸を垂らすと、ビールのように音を立てて泡立つ。写真は方解石だ。石灰岩は広く分布しているので、それとわかれば有力な判断材料になる。採集時も希塩酸を目薬容器に入れて持参する。 ブラックライトで紫外線を当てると蛍光を発する鉱物があるので、鑑定の手がかりになる。写真は燐灰ウラン鉱で、左が通常光、右は紫外線を当てて蛍光を発した状態だ。ウラン鉱物は黄色いものが多く、核燃料の原料になる粉末もイエローケーキという。紫外線を当てると黄緑色の強い蛍光を発するが、放射能とは関係ない。紫外線のエネルギーを受けて励起された原子が発する光で、仕組みは次に述べる炎色反応とほぼ同じだ。
ブラックライトで紫外線を当てると蛍光を発する鉱物があるので、鑑定の手がかりになる。写真は燐灰ウラン鉱で、左が通常光、右は紫外線を当てて蛍光を発した状態だ。ウラン鉱物は黄色いものが多く、核燃料の原料になる粉末もイエローケーキという。紫外線を当てると黄緑色の強い蛍光を発するが、放射能とは関係ない。紫外線のエネルギーを受けて励起された原子が発する光で、仕組みは次に述べる炎色反応とほぼ同じだ。
写真の青い扇形の器具は教材用の簡単な分光計で、光源に向けて接眼部を覗くと虹のように分かれた光が目盛りの上に現れる。
次の写真は神岡で拾ったブロシャン銅鉱の炎色反応だ。ハンマーで砕いたあと乳鉢で擦って粉末にした。銅鉱だから銅の炎色が顕著に現れる。


熱源の炎は無色に近いほどいいので、ガスバーナーが推奨されている。しかしちょっと気忙しいので、私はアルコールランプにガラス繊維の芯を挿して使っている。木綿の芯はナトリウムを含むのか、炎がオレンジ色になってしまう。

原子は原子核のまわりに電子の殻があって、太陽をまわる惑星軌道のように入れ子になっている。ここに熱エネルギーを加えると、電子は高い軌道にぴょんと移動し、また元の軌道に戻る。
じわじわアナログ的に移動するのではなく、決まった間隔で「ぴょんと移動する」のが面白いところだ。この説明では軌道に例えているが、電子はもっとわけのわからない存在で、原子核のまわりにある雲のような領域で暮らしている。それでもエネルギーによってぴょんと移動するところは変わらない。(このあたりを調べるならキーワードは自然放出、励起状態、基底状態など)
エネルギーによって色が変わるのは、人間の眼がそう知覚するようにできているからで、ローカル仕様にすぎない。宇宙共通の表現を心がけるなら、色ではなくエネルギー、もしくはエネルギーに対応した波長を示すのが適切だろう。
2010年6月13日、はやぶさ探査機がオーストラリア上空で大気圏に突入したとき、私はニコニコ生放送で実況するため、現地で取材していた。バックカントリーを南北に貫くスチュアート・ハイウェイのパーキングエリアに陣取り、夜を待った。
 宵のうちはよく晴れていて、降るような星空だったが、21時頃から雲が出始めた。
宵のうちはよく晴れていて、降るような星空だったが、21時頃から雲が出始めた。22時51分、西の低い空で雲が急に照らされ、無数の光の束がこちらに向かって来た。先行する黄色い光点は再突入カプセルで、気化した融除シールドによる糸のような尾を引いていた。はやぶさ本体の光の束は爆発的に拡がり、影が落ちるほどになった。緑とピンクの閃光が交互に現れ、最後の爆発では全天がワインレッドに染まった。
「あれは古河電池のリチウムイオン電池だな」と直感した。動画を見ると、本体が燃え尽きる直前、大きな塊が上下に分離する。この光がリチウムの炎色を放ったようだ。
後日、阿部新助先生らが行った分光観測の分析からそのことが確かめられた。

阿部先生は天然の流星で分光観測をしていて、流星群のときNASAの観測機に乗ったりもしていた。流星にも珪素質、炭素質、金属質などの種類があり、それを反映した炎色を発するから、分光観測すればその成分がわかる。流星の多くは彗星が撒いたダストなので、母体になった彗星の成分もわかる。
「一を聞いて十を知る」というが、相手が宇宙となると十どころか万、億、兆と際限なくスケールする。にもかかわらず、ルールはひとつのままだ。これは知識の獲得手段として素晴らしい効率といえよう。鉱物学や地球科学、それらの根源にある物理学と数学は天に掛けた梯子なのだ。
野尻抱介

SF作家、Maker、ニコニコ技術部員。1961年生まれ。三重県津市在住。計測制御・CADのプログラマー、ゲームデザイナーをへて専業作家になったが、現在は狩猟を通して自給自足を模索する兼業作家。『ふわふわの泉』『太陽の簒奪者』『沈黙のフライバイ』『南極点のピアピア動画』ほかで星雲賞7回受賞。宇宙作家クラブ会員。第一種銃猟免許、わな猟免許所持、第三級アマチュア無線技師。JQ2OYC。Twitter ID @nojiri_h